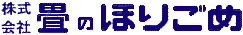畳のほりごめ さんの日記
2023
8月
26
(土)
16:56
チコちゃんに叱られない
 前の日記
次の日記
前の日記
次の日記 カテゴリー
社長のぼやき(^^;
カテゴリー
社長のぼやき(^^;
本文
畳の大きさが地方によって違っていることは、ちょっと詳しい方ならご存知だと思います。
https://www.horigome.co.jp/modules/xpwiki/318.html
で、その理由が結構間違って紹介されていて、私が考察して否定した記事も書いていました。
これと同様な意見は、今までどこにも見当たらなかったのですが、はじめてテレビで同意できる内容を見ることが出来ました。
https://www.nhk.jp/p/chicochan/ts/R12Z9955V3/episode/te/JVY69MJLPL/
内容を補足しておくとすれば、検地の規準がなぜ建物の規準になったのか?という点でしょう。
これはおそらく、1間(いっけん)という規準が、検地尺(検地棒・ 間竿(けんざお))によって明確になり、手近に手に入る「公的基準の長さ」だったからだと思われます。
*例えば、作業場の1間と、現地の1間が同じ長さであれば、部材を作るのに便利だから。
また、その基準が便利だとすると、多数派となり大量生産に向いてくるので一気に寡占していきます。
実際に、今でもベニヤ板などを買いに行くと、三六板(さぶろくばん)と言って、3尺×6尺のものが大半を占めています。
この大きさは、畳に限ったものではなく、襖や障子も同様(建物の柱間による)の理由で、三六サイズが多いわけです。
さて、検地の1間よりも畳のほうが若干小さかったことに気がつかれた方も多いと思います。
実は、柱と畳の間には、敷居があったりするんです。そうすると後から作る畳は、その分小さくなる、というわけです。
ちなみに、秀吉が定めた検地に関しては、長さの基準も定めていて、検地尺が現存しています。
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402331_00000
解説にはありませんが、この板に「石田」と書かれており、石田三成が検地に関して「この長さを使って、1間を6尺3寸とする」と定めています。
https://www.horigome.co.jp/modules/xpwiki/318.html
で、その理由が結構間違って紹介されていて、私が考察して否定した記事も書いていました。
これと同様な意見は、今までどこにも見当たらなかったのですが、はじめてテレビで同意できる内容を見ることが出来ました。
https://www.nhk.jp/p/chicochan/ts/R12Z9955V3/episode/te/JVY69MJLPL/
内容を補足しておくとすれば、検地の規準がなぜ建物の規準になったのか?という点でしょう。
これはおそらく、1間(いっけん)という規準が、検地尺(検地棒・ 間竿(けんざお))によって明確になり、手近に手に入る「公的基準の長さ」だったからだと思われます。
*例えば、作業場の1間と、現地の1間が同じ長さであれば、部材を作るのに便利だから。
また、その基準が便利だとすると、多数派となり大量生産に向いてくるので一気に寡占していきます。
実際に、今でもベニヤ板などを買いに行くと、三六板(さぶろくばん)と言って、3尺×6尺のものが大半を占めています。
この大きさは、畳に限ったものではなく、襖や障子も同様(建物の柱間による)の理由で、三六サイズが多いわけです。
さて、検地の1間よりも畳のほうが若干小さかったことに気がつかれた方も多いと思います。
実は、柱と畳の間には、敷居があったりするんです。そうすると後から作る畳は、その分小さくなる、というわけです。
ちなみに、秀吉が定めた検地に関しては、長さの基準も定めていて、検地尺が現存しています。
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005402331_00000
解説にはありませんが、この板に「石田」と書かれており、石田三成が検地に関して「この長さを使って、1間を6尺3寸とする」と定めています。
閲覧(192512)
| コメントを書く |
|---|
|
コメントを書くにはログインが必要です。 |